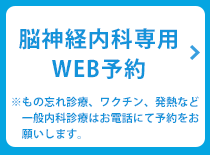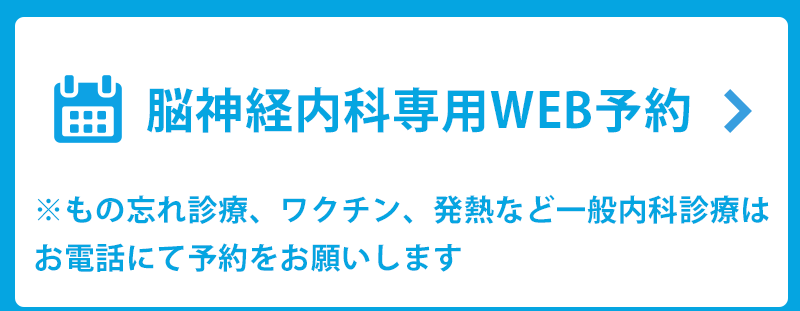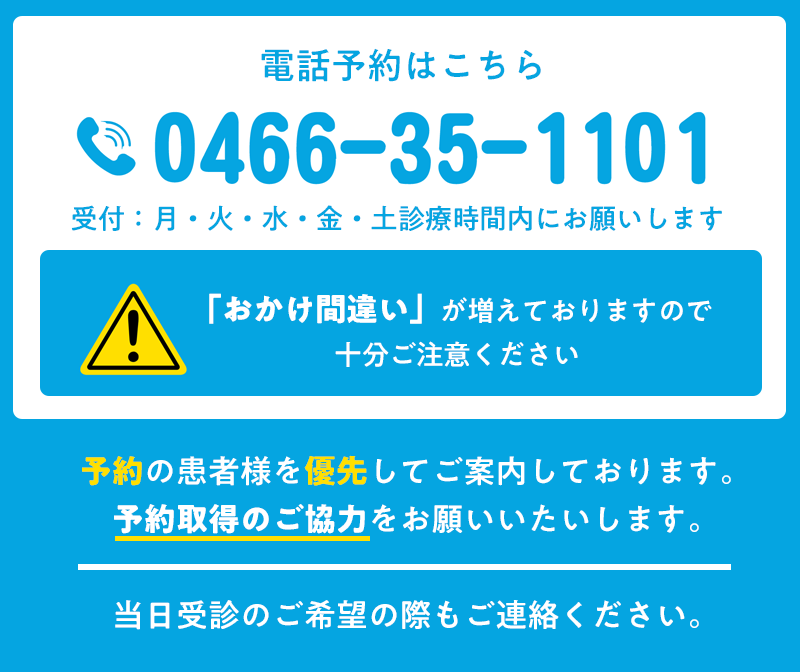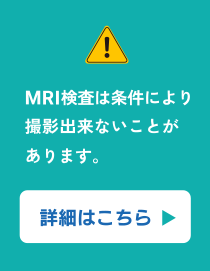脳の病気と症状
脳の血管の病気
1. 脳卒中とは?
脳卒中は、①血管がつまる「脳梗塞」、②血管が破れて出血する「脳出血」、③「くも膜下出血」の大きく3つに分けられます。寝たきりになる原因の中でも大きな割合を占める脳卒中は、生活習慣病の増加や高齢化社会に伴い増加傾向にあると言われています。
症状は麻痺、しびれ、嘔吐、ろれつ障害、意識障害、頭痛など、病気が起こった脳の場所により症状は異なります。もし突然このような症状が出現したら、ただちに受診が必要となります。
症状は麻痺、しびれ、嘔吐、ろれつ障害、意識障害、頭痛など、病気が起こった脳の場所により症状は異なります。もし突然このような症状が出現したら、ただちに受診が必要となります。

2. 脳梗塞
脳梗塞とは、脳の血管が詰まったりすることで、その先の脳細胞が障害を受ける病気です。原因としては血管の老化である動脈硬化や、心臓の不整脈により血栓ができてしまう状況などが考えられます。高血圧、高コレステロール、糖尿病、喫煙などが危険因子と考えられています。

一度起こしてしまった脳梗塞を治すことはできません。起こさないように日ごろから危険因子をなるべく取り除く努力が必要です。また、高血圧、高コレステロール、糖尿病などをしっかり治療することが重要です。また、次に発症しないために血液を固まりにくくする薬を使用することもあります。
3. 脳出血
脳血管が破れることにより、脳内で出血した状態を指します。脳出血の原因は高血圧であることが多いですが、脳動静脈奇形やモヤモヤ病のような血管の形の変化により出血をする場合もあります。

4. くも膜下出血
脳の動脈にこぶ(脳動脈瘤)生じ、次第に大きくなり、破裂するのがくも膜下出血です。出血は脳全体へ広がり激しい頭痛と嘔吐をきたします。教科書的には「突然後ろからバットで殴られた」ような、今までに感じたことがない程の痛みであることが特徴です。高血圧との関連が指摘されています。

頭痛
皆さんが感じる頭痛は、ガイドラインでは大きく3つに分類されます。
①一次性頭痛:はっきりとした原因が分かりにくく、多くの場合は様々な要因が複合的に絡み合って発症する頭痛
例えば、片頭痛、群発頭痛、肩こりとの関連が指摘される緊張型頭痛など
②二次性頭痛:他の頭蓋内の原因により発生する頭痛
例えば、くも膜下出血、脳しゅよう、感染症など
③その他頭痛
①一次性頭痛:はっきりとした原因が分かりにくく、多くの場合は様々な要因が複合的に絡み合って発症する頭痛
例えば、片頭痛、群発頭痛、肩こりとの関連が指摘される緊張型頭痛など
②二次性頭痛:他の頭蓋内の原因により発生する頭痛
例えば、くも膜下出血、脳しゅよう、感染症など
③その他頭痛
多くの場合は一次性頭痛ですが、まれに二次性頭痛やその他頭痛が原因となっている場合もあります。中には危険な病気の前兆であることもあり、初めて強い頭痛を感じた際は受診を強くお勧めします。
一次性頭痛であったとしても、お薬の調整、変更でさらに楽になったり、市販薬の使い過ぎによりかえって頭痛が慢性化してしまう薬物乱用性頭痛になっておられる方も多々お見受けします。いままでの頭痛でもつらいな、心配だなとお感じの場合は一度専門医療機関にご相談ください。
一次性頭痛であったとしても、お薬の調整、変更でさらに楽になったり、市販薬の使い過ぎによりかえって頭痛が慢性化してしまう薬物乱用性頭痛になっておられる方も多々お見受けします。いままでの頭痛でもつらいな、心配だなとお感じの場合は一度専門医療機関にご相談ください。

しびれ
しびれには、手や足に力が入りにくくなる運動麻痺と長く正座した後のようにジンジンする感覚異常の場合とがあります。
運動麻痺と感覚異常が同時に起こる場合もあります。
運動麻痺と感覚異常が同時に起こる場合もあります。

脳疾患に原因がある「しびれ」
脳出血・脳梗塞などの脳血管障害が主な原因です。多くの場合、大脳や小脳と左右が反対側の手足や顔などにしびれが起こります。また、視床と呼ばれる部位に障害が起こると、「しびれ」だけではなく強い痛みがともなう場合があります。
短時間で良くなる繰り返す手足のしびれは、脳梗塞の前触れである「一過性脳虚血発作」の場合があり注意が必要です。
脳腫瘍の場合、病気が進行するとしびれや感覚麻痺が強くなります。
脊椎・脊髄疾患に原因がある「しびれ」
変形性頚椎症、頚椎椎間板ヘルニア、頚椎後縦靭帯骨化症、胸郭出口症候群、手根管症候群など内科的疾患に原因がある「しびれ」
糖尿病による末梢神経障害やビタミン欠乏症による末梢神経障害なども「しびれ」の原因になります。「しびれ」の原因は脳や脊椎、末梢神経、内科的疾患など色々ありますが、特に血管障害や脳腫瘍は、命に関わる可能性や重大な後遺症が生じる場合もあります。
当院ではしびれの原因を放射線被曝の心配がない最新鋭の1.5テスラMRI装置を使って検査を行い、原因を精査した上で適切な治療を行います。
めまい
「めまい」で外来を受診される患者様のうち、その多くは内耳の障害による良性発作性頭位めまいや前庭神経炎、ストレスやウイルス感染によるメニエール病や突発性難聴が多いとされています。
脳が原因となる「めまい」は比較的まれですが、脳血管障害(椎骨脳底動脈循環不全、脳出血、脳梗塞)や脳腫瘍などの深刻な病態に関連している場合もあり適切な診断と治療が必要です。
脳が原因となる「めまい」は比較的まれですが、脳血管障害(椎骨脳底動脈循環不全、脳出血、脳梗塞)や脳腫瘍などの深刻な病態に関連している場合もあり適切な診断と治療が必要です。
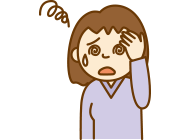
「めまい」にお悩みの方、特に以下のような症状がある場合には医療機関の受診をお勧めします
•天井が回るような感覚
•体が浮遊しているような感覚
•頭を急に動かした時にめまいがする
•気が遠くなりそうな感覚
•天井が回るような感覚
•体が浮遊しているような感覚
•頭を急に動かした時にめまいがする
•気が遠くなりそうな感覚
「めまい」の原因となる脳疾患には、脳血管障害や脳腫瘍が含まれます。脳の血流不足により小脳や脳幹の機能に影響を及ぼし、「めまい」以外にも舌のもつれ、物が二重に見える、手足のしびれなどの症状を引き起こす場合や脳出血の可能性も考慮されます。
脳腫瘍では「めまい」以外にも慢性的な頭痛、吐き気、嘔吐、視力低下などが起きることもあります。
脳血管障害や脳腫瘍は、命に関わる可能性や重大な後遺症が生じる場合もありますので、なるべく速やかに診療機関を受診して下さい。
当院では 最新鋭の1.5テスラMRI装置を導入し、放射線被曝の心配なく、非常に精度の高い検査を快適に受けていただける環境を整え正確な診断を行います。
てんかん
てんかんと聞くと、「お子さんの病気でしょ?」と言われることが多々あります。
私たちの脳の中は、神経細胞が電線の様につながり、電気や化学物質のやり取りをすることで機能しています。この電線からの漏電により、過剰な電気が流れてしまうことで発生する症状がてんかんです。
ですから、初めて症状が出る年齢は小児期に限ったことではありません。
どの場所で過電流となってしまうかで、どのような症状が出るかが違ってきます。
症状としては、意識を失い、全身をがくがくさせる「けいれん」が多いですが、中には発作的にぼーっとしてしまうだけの症状、発作的な行動異常などの症状であることもあり、周囲の方から見るあたかも「認知症」のように見える発作の方もおられますので注意が必要です。
また、脳しゅようなど他の病気の症状の一つであることもありますので、気になられる方は一度専門医の受診をお勧めします。
私たちの脳の中は、神経細胞が電線の様につながり、電気や化学物質のやり取りをすることで機能しています。この電線からの漏電により、過剰な電気が流れてしまうことで発生する症状がてんかんです。
ですから、初めて症状が出る年齢は小児期に限ったことではありません。
どの場所で過電流となってしまうかで、どのような症状が出るかが違ってきます。
症状としては、意識を失い、全身をがくがくさせる「けいれん」が多いですが、中には発作的にぼーっとしてしまうだけの症状、発作的な行動異常などの症状であることもあり、周囲の方から見るあたかも「認知症」のように見える発作の方もおられますので注意が必要です。
また、脳しゅようなど他の病気の症状の一つであることもありますので、気になられる方は一度専門医の受診をお勧めします。

認知症
「最近、テレビに出ている芸能人の名前が出てこなくて・・・」などとおっしゃられ、認知症が心配とご相談に来られる方が多くなっています。
認知症の定義は、「正常に達した知的機能が後天的な器質性障害によって持続的に低下し、日常生活や社会生活に支障をきたすようになった状態」(日本認知症学会編、認知症テキストブックより)であり、つまり、「問題なく生活をする知能を持っていた方が、知能低下が進行してしまい、日ごろの生活に支障がでている状態」が認知症である、ということになります。
先述の名前が出てこないという症状は、生活に支障がない範囲であれば、知能低下とまではいいがたく、まずはご年齢による生理的な記憶障害の影響であることが多いです。しかし、認知症の検査をしてみると、意外にも失点が多く、ご本人のみならずご家族もその状況に気づいていなかったという事態に遭遇することもあり、少しでも気になるようであればご相談にいらっしゃることをお勧め致します。
認知症には、①アルツハイマー病、②レビー小体病、③前頭側頭葉変性症、④脳血管性認知症、その他など数種類あり、今の医学では、いずれの病気も根本治療は難しいですが、一番頻度の多いアルツハイマー病については現在4種類の治療薬の保険適応が認可されています。いずれも、症状の進行を遅らせる効果などを認めており、より早期から使用することで効果が期待できるとの報告もあり、早い段階での診断が重要であると考えられています。
また、軽度認知機能障害(MCI)という概念もあり、「認知症とは言えないが、完全に問題なしとも言えない状態」が確認されるケースもあります。この場合、一部の方は進行なく経過されますが、多くの方は5~6年程度で認知症に至ったという報告もあり、早期から生活指導や、メタボリック症候群に対する治療をおこなうことで進行を予防しようという試みもされています。
治療可能な認知症といわれる状態もあり、ご家族が「認知症」と思われていても、実は「慢性硬膜下血種」や「甲状腺機能異常」、「てんかん」、「ビタミン欠乏」などが原因となっていることもあります。これらは各々の治療で症状が回復される場合もあるので、「認知症」を疑った場合は、専門医療機関を受診し、しっかり診察、検査を行うことが重要です。
認知症の定義は、「正常に達した知的機能が後天的な器質性障害によって持続的に低下し、日常生活や社会生活に支障をきたすようになった状態」(日本認知症学会編、認知症テキストブックより)であり、つまり、「問題なく生活をする知能を持っていた方が、知能低下が進行してしまい、日ごろの生活に支障がでている状態」が認知症である、ということになります。
先述の名前が出てこないという症状は、生活に支障がない範囲であれば、知能低下とまではいいがたく、まずはご年齢による生理的な記憶障害の影響であることが多いです。しかし、認知症の検査をしてみると、意外にも失点が多く、ご本人のみならずご家族もその状況に気づいていなかったという事態に遭遇することもあり、少しでも気になるようであればご相談にいらっしゃることをお勧め致します。
認知症には、①アルツハイマー病、②レビー小体病、③前頭側頭葉変性症、④脳血管性認知症、その他など数種類あり、今の医学では、いずれの病気も根本治療は難しいですが、一番頻度の多いアルツハイマー病については現在4種類の治療薬の保険適応が認可されています。いずれも、症状の進行を遅らせる効果などを認めており、より早期から使用することで効果が期待できるとの報告もあり、早い段階での診断が重要であると考えられています。
また、軽度認知機能障害(MCI)という概念もあり、「認知症とは言えないが、完全に問題なしとも言えない状態」が確認されるケースもあります。この場合、一部の方は進行なく経過されますが、多くの方は5~6年程度で認知症に至ったという報告もあり、早期から生活指導や、メタボリック症候群に対する治療をおこなうことで進行を予防しようという試みもされています。
治療可能な認知症といわれる状態もあり、ご家族が「認知症」と思われていても、実は「慢性硬膜下血種」や「甲状腺機能異常」、「てんかん」、「ビタミン欠乏」などが原因となっていることもあります。これらは各々の治療で症状が回復される場合もあるので、「認知症」を疑った場合は、専門医療機関を受診し、しっかり診察、検査を行うことが重要です。